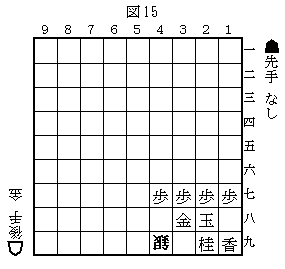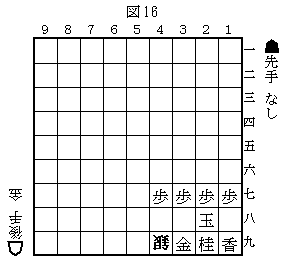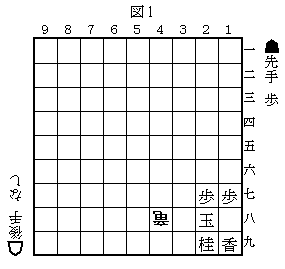
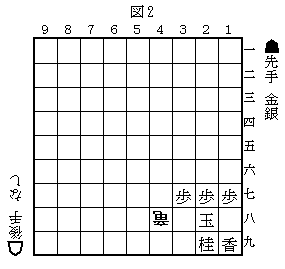
攻めるのは得意ですが、受けが苦手という方は多いと思います。 ここでは、受けの基本について紹介します。
図1を見て下さい。 図1では、竜による王手がかかっています。 玉の逃げ道はありませんので、持ち駒を38の地点に打つことになります。 このように、飛び駒(飛車、角、香車)による王手に対して、 持ち駒を打つなどして、王手を防ぐことを合い駒をするといいます。 図2では、先手の持ち駒に金と銀があります。 どちらを合い駒するのがいいでしょうか。 この場合は金を打つと相手の竜への取りになっています。 銀を打つと相手の竜は逃げなくても大丈夫になります。 このように相手の駒に当てることで、先手を取ることができる場合もあります。
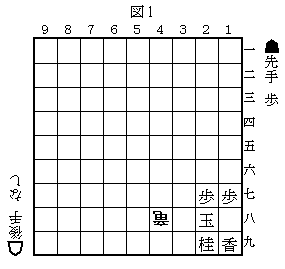
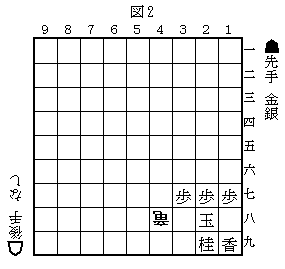
図3では、角による王手がかかっています。 まず、37地点に何か駒を打つのが考えられます。 この時、飛車を打つと、図4のように36歩とされて飛車を取られてしまいます。 これは香、桂、銀、金でも同様です。 歩の場合も36歩とされて依然として受けづらい形です。 角の場合はどうでしょうか。 図5のように金を打たれ、これもあまり思わしくはありません。 困ったようですが、図6のように46に歩を打つ手筋があります。 同角ならば、37銀もしくは37金と先手を取って、73角と逃げたら、 46歩と角道を封鎖して受けることができます。
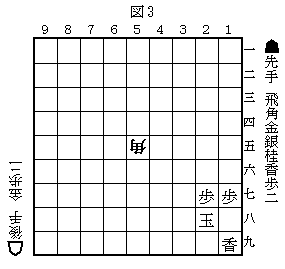
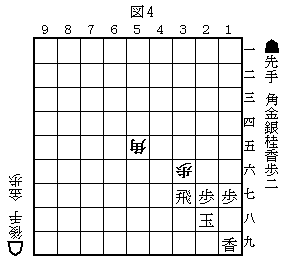
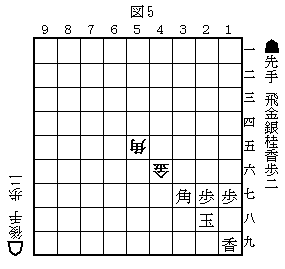
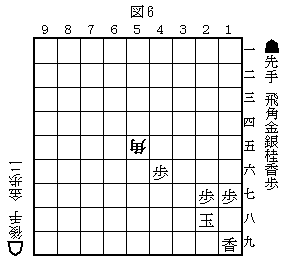
図7も図1や図2のように竜による王手がかかっています。 持ち駒の金を38に打って、先手を取って良いようですが、 39銀と打たれて詰んでしまいます。 困ったようですが、29の銀を38に移動すると、 39銀とされても29玉として、図8のようになり詰みから逃れています。 このように盤上にある駒を移動させて、王手を防ぐ合い駒を移動合いと言います。
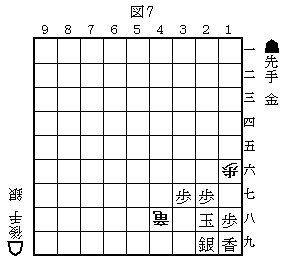
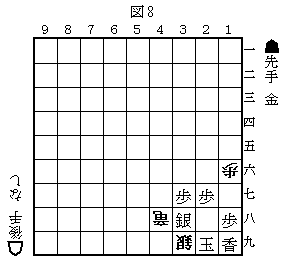
図9は香車による王手がかかっています。 持ち駒もなく、18玉と逃げても27桂成、29玉、28歩以下詰んでしまいます。 これも困ったようですが、26桂と跳ねる手がありました。 以下、同香に38玉と、図10のように逃げ出すことに成功します。 この桂馬のようにただで取られる位置に駒を捨てて、 逃げ道を開ける、移動合いを移動捨て合いと言います。
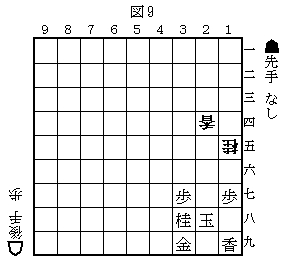
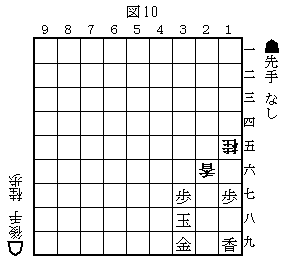
図11は飛車による王手がかかっています。 先手の持ち駒はたくさんありますが、何を合い駒するのがよいでしょうか。 いづれも後手は取ってきます。少し考えて見て下さい。 まず、歩を合い駒してみます。 すると、同飛成、同玉、28歩、19玉、39竜と図12のように進んで詰んでしまいます。 香を合い駒する場合も、歩と同様ですし、 金、銀の場合は、同飛成から28金または銀と3手で詰んでしまいます。 今見てきたように、「頭に利く駒(歩、香、銀、金、飛)」はワンセットで考えることが重要です。 歩で詰む場合は、他の頭に利く駒でも詰んでしまうことが多いです。 となると、「頭に利かない駒(桂、角)」を次に考えます。 まず、桂馬ですが、同飛成、同玉、37桂、19玉、39竜と図13のようになって詰みです。 角の場合はどうでしょうか。 やはり、同飛成から38角、28玉と図14のようになります。 この図はいかにも詰みそうですが、詰みを逃れています。 考えて見て下さい。
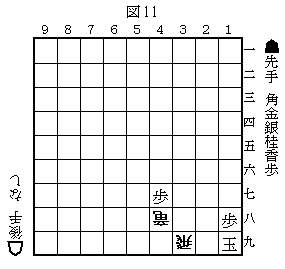
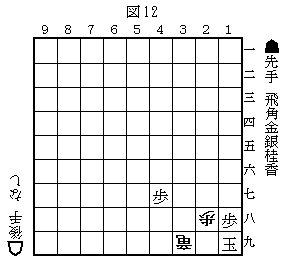
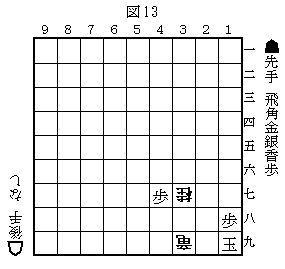
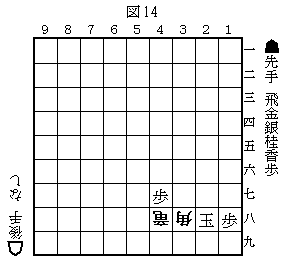
図15は守りの金に銀をかけられたところです。 よくある攻めで、このまま金をはがされると、 いつでも詰みが生じる形となり危険です。 そこで、金を39金と図16のようにかわします。 これで、相手の持ち駒が金だけでは、後手はうまく攻めることができません。 同じだと思って、金を48にかわすと、58金とからまれて、 攻めを振りほどくのが難しくなります。